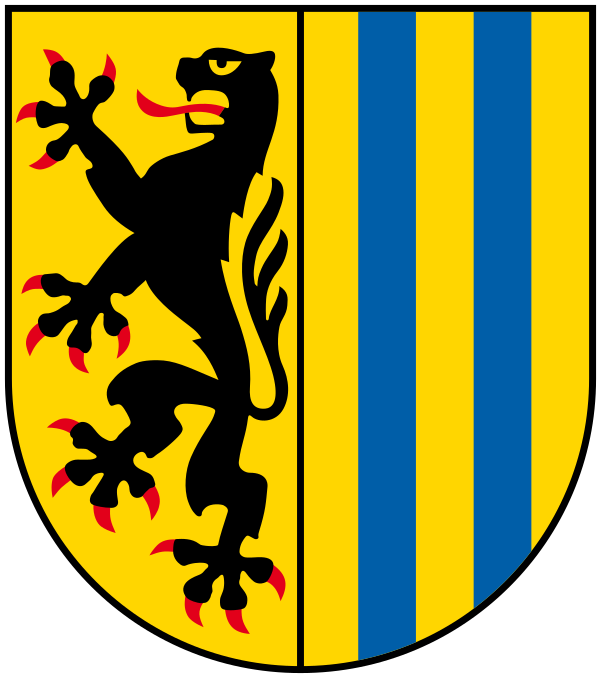von Hagen, Mark. “Revisiting the Histories of Ukraine,” in Georgiy Kasianov/ Philipp Ther (ed.), A Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Budapest/N.Y., 2009
Ther, Philipp. „Die Nationsbildung in multinationalen Imperien als Herausforderung der Nationalismusforschung,“ in Andreas Kappeler (Hg.), Die Ukraine: Prozesse der Nationsbildung. Köln/Weimar/Wien, 2011
Wendland, Annna Velonika. „Ukraine Transnational: Transnationalität, Kulturtransfer, Verflechtungsgeschichte,“ in Andreas Kappeler (Hg.), Die Ukraine: Prozesse der Nationsbildung. Köln/Weimar/Wien, 2011
いずれも、「ウクライナ史」へのアプローチに関する、最新の研究動向を踏まえての問題提起。
von Hagenはかつての挑発的なvon Hagen, Mark. “Does Ukraine Have a History?” in Slavic Review 54-3, 1995を振り返りながら、現在注目すべき視点をいくつか挙げている。境界領域、地域などはスラ研のおかげもあって馴染みがあるが、都市という視点はあまりとられていないように感じる(リヴィウは例外)。ともかく、多様性こそにウクライナ史の特徴があるという論点は、1995年から変わっていない。
Therは帝国という場への視点が今までのナショナリズム論に欠けていたと指摘し、ネイションと帝国政府の相互作用や、「ネイション化する帝国(ドイツやロシア)」とその臣民であるネイションのナショナリズムとの緊張関係などに着目すべきと述べる。また、ナショナリズム内部の潮流においても、帝国や王朝原理に迎合的なものが存在する場合がある。いずれの視点も、ウクライナ史によくあてはまっており、今後の可能性を感じさせる。
Wendlandはトランスナショナルヒストリー、文化交換、絡み合いの歴史の視点をウクライナ史に導入した。ウクライナ・ネイションビルディングは、フロフ論のような内在的な語りでは捉えられないトランスナショナルな運動だった。ドニプロとガリツィアの知的交流、ポーランド人からの民族理論の吸収、ディアスポラから、反ユダヤ主義、ホロドモル、ナチとの協力などの負の側面まで、ウクライナ史は文化交換と絡み合いに満ちている。さらに、相互作用の特に濃密だった都市や境界地域
、そしてそこでの同化と異化についても、研究が期待される。最後に著者は、既にウクライナのトランスナショナルな面を鋭く指摘し、自らが文化交換の主体として活動してきたミハイロ・ドラホマノフに注目する意義を、改めて述べている。
第一次世界大戦におけるウクライナ・ナショナリズムについて、ドイツ・オーストリアとウクライナ人インテリの間の文化交換を通して語ることは可能かもしれない。